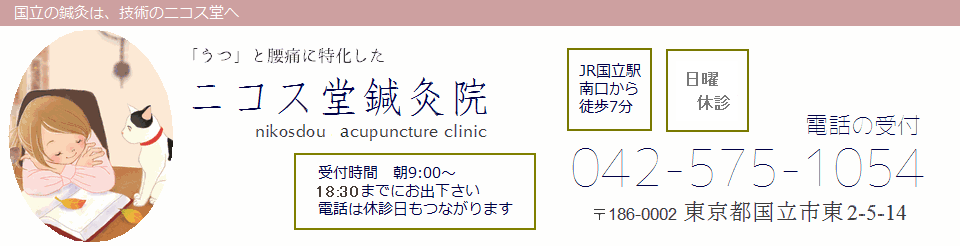|
| |
森しげ伝 1 <男の声に魅せられて>
年始にかけて、ずっと森鷗外の家族の書いた本を読んでいました。鷗外は、明治から大正にかけての文壇の巨人で、また退役までは陸軍の医官の最高峰にいた人でした。
退官後は、いまの国立国会図書館、国立博物館の館長を歴任しました。奥さんは前後して二人いて、最初の妻との間には一男、二人目の妻との間には一男二女をあげ、この四人がいずれも鷗外の思い出を書いています。私もすべてを読んだわけではありませんが、次女杏奴(あんぬ)の書いた「晩年の鷗外」(岩波文庫)には、つよく心を惹かれました。
鷗外周囲の人物のなかで、もっとも興味ひかれる人といえば、二番目の奥さんの「しげ」さんでしょう。一言でいえば甘やかされたお嬢さんで、冗談の通じなかった人だったといいます。また当時の評判の美人で、気難しい鷗外の母親もはじめは、あんな美しい人に、きれいな着物をきせて家の中に座らせておいたら、どんなにか愉しかろうと言っていました。当時の写真が今でもあり、これを見ると、この手の美人は今でもいる、とすぐに思い浮かびます。
しげさんは、はじめ「舞姫」「文づかひ」などの鷗外の小説中の男性に恋し、次いで鷗外その人に恋しました。当時、鷗外は軍人でしたから、真っ黒に日焼けし、鼻の頭もてかてかに光っていましたが、落着いた物腰と、柔らかい声がよかったと、そののち娘に打ち明けています。
このとき鷗外四十一才、しげ二十三才で、どちらも最初の結婚に失敗したものどうしでした。十八の年が離れていますが、この「声に魅せられた」というところが、ミソだろうと私は思っています。
男子が声変わりするのは、二次性徴期です。つまり性的なエネルギーの力で、変声は起こります。ですから、男の声に魅了される女性というのは、そのまま相手の性的エネルギーにひかれていると見ることができます。裏がえして、女性の声というのも、またなまめかしいものです。とくに四十を過ぎた女性の深く落着いた声というものには、素晴らしい魅力があります。
絶世の美人ですから、鷗外もしげさんに惚れます。折りしも鷗外は九州の小倉に左遷されている最中で、邪魔するものもありません。こののち半年ほど、二人は小倉で幸福な時間を過ごします。東京に帰ってきたあとには地獄のような日々が待っているのですが、それは次回に。
|
|
| |
| |
森しげ伝 2 <おれの妻のやうな女はない>
しげさんは、当日の最高裁判事の娘で、明船町の広大な屋敷で甘やかされて育った評判の美人でした。それに加えて、周りの空気が読めなかったり、すぐにプツンとキレてしまったりと、この人には発達障碍があったのではと思わざるを得ません。
はじめ、美貌を買われて資産家の息子と結婚しますが、将来の約束のあったらしい芸妓が騒ぎはじめたので、父親が怒って別れさせます。結婚してひと月も経たないうちのことですから、しげさんは何が何だか分りません。
それが今度は、自分の愛読していた本の著者と結婚できて、邪魔するものもない九州で暮らせるのですから、夢のような時間です。
こんど帰ってくる東京の鷗外の家は、つつましさの極みのような家で、母親のみねは裁縫のあとの糸の一本までとっておいてつなぎ合わせ、丸い玉にしておいたものを、今度は布団のカバーに織ってもらうような人です。おまけに勝気で、長男林太郎(鷗外)の月々のものも、自ら管理しています。
しげさんは、とにかくまじめな人で、冗談を嫌い、軽薄さを徹底的に憎んだ人でした。こんな女性は、火の出るような激しい男と惚れ合うのかと思いますが、鷗外という人は反対に、どちらかというと曖昧な人で、本の埃をはらうような小さな仕事を、いかにも落着いて嬉しそうにする人でした。その嬉しい楽しい雰囲気が周囲にもあふれ出て、子供たちも落着くのです。次女の杏奴は、夫婦の愛の雰囲気も父がひとりでかもし出しているものだったと書いています。鷗外といえば、明治・大正の文壇の頂点にあった人で、さまざまな論争に自ら参加して相手をうち負かしたひとでしたから、この姿は意外です。
問題は、鷗外にとっては、何よりも親孝行が絶対至上だったということで、ここを少し和らげれば、夫婦の仲ももう少しなめらかになったはずです。ここだけは、次女の杏奴も父にたいして批判的です。
さて、しげさんは九州の小倉から帰ってきたときだけは、鷗外の母親に頭を下げましたが、次第におはようございますも言わなくなります。「一通りの人ではないのですものを。お金はみんな持つて行つて、好い加減にしていて、あなたをまで取つてしまはうと思つているのですものを。ちよいと油断をすると、すぐあなたの側へ來る。あなたにはあれが當前に見えて。えゝ。氣味が惡い。」「丸であなたの女房氣取で。会計もする。側にもゐる。御飯のお給仕をする。お湯を使ふ處を覗く。寝てゐる處を覗く。色氣違いが。」 [森鷗外「半日」]
姑との間がこじれたあげく、しげさんは生まれて間もない長女(茉莉)をつれて、明船町の実家の離れで暮らすようになります。そこへ鷗外は2,3日おきにやって来ます。
鷗外はしげさんの状態を、性欲がおかしな方向にそれた倒錯状態ではないかと考えていたようですが、この当時の考え方としては、それが妥当だったのかもしれません。が、現今ではやはり発達障碍を考えるのが、もっとも適しているのではないでしょうか。
この後、日露戦争が始まり、鷗外も従軍して戦地に向かうことになります。しかし離れることで、二人の仲は、今度はぐっと近づくようになりました。 |
(写真・鷗外の母・峰) |
|
| |
| |
森しげ伝 3 <はなの香する君あらなくに>
鷗外は日露戦争では第二軍軍医部長として従軍しました。司令官は奥保鞏で、「坂の上の雲」にも、勇敢かつ兵をいたわる魅力的な司令官として描かれていた軍人です。
戦争中、離ればなれになっていることでお互いの気持ちはぐっと近くなります。
ゆくりかに胸こそさわげ何処ゆかばはなの香する君あらなくに
いくたびか君ゐますかと書室の遣戸の引き手ひかんとはせし
いたづらに夕とどろく虎の門吾せの乗らすあをうまの來ぬ
これらは、日本から届いたしげさんの歌を、鷗外が添削して作としたものです。
やがて戦も終わり、鷗外も日本に帰ってきます。帰ったら必ずその日のうちに明船町の家に行くと、戦地から手紙で知らせていましたが、帰国当日は妻のもとへ直行できるはずもありません。新橋の駅は、凱旋兵士を迎える群衆で溢れかえっています。軍の幹部は、駅に到着するやそのまま馬車で宮中に行き、戦勝の報告をしなければなりません。それが終わって千駄木の家に帰れば、今度は親戚・近所一同がお祝いのために待ち構えています。
最後の客が帰ったのは夜の12時すぎで、それから鷗外は無言のまま拍車のついた長靴を履き、2時間かかって凍った道を明船町まで歩いてやってきたといいます。
まもなく、しげさんは義母とも融和して、ふたたび千駄木の家に戻ることになります。
このとき、鷗外の子供は、前妻の子・於菟(おと)、しげさんの上げた長女・茉莉(まり)がいます。この後、千駄木の家で、半子(はんす・男)、不律(ふりつ・男)、杏奴(あんぬ・女)、類(るい・男)と生まれますが、未熟児だった半子は生まれて間もなく死にます。
茉莉と不律は百日咳にかかりますが、床に就いたままの幼いわが子が苦しむのを、鷗外は見ていられません。とくに不律は母親に似て見目うるわしい赤子で、鷗外と目が合うたびに、にっこりと微笑みます。病の床にあっても、鷗外と目が合うと笑おうとするので、鷗外の胸ははり裂けます。
とうとう鷗外は、主治医に安楽死の処置をつげ、不律は亡くなります。
この時、茉莉もおなじ病で生死の境をさ迷っていますが、日を置いて、いよいよ茉莉にも安楽死の用意がされたとき、偶然に於菟の祖父である赤松義則がやってきて、皆を一喝します。その後、奇跡的に茉莉はもち直して一命をとりとめるのですが、茉莉は生涯この祖父を徳として敬ったといいます。
しげさんは、二人の看病の間に不思議な夢を見ています。二人の子供を連れて湯屋へゆくのですが、そこで二人を湯船で溺れさせてしまう夢でした。急いで湯から引きあげて医者へ連れてゆきますが、女の子だけ息を吹き返し、男の子は硬直したまま医師の手から返されるという、これは正夢でした。 |
| |
|
| |
| |
森しげ伝 4 <夫を完全に独占したい>
明船町から千駄木の家に戻ったしげさんですが、鷗外の母親・みねだけでなく、先妻の子である於菟(おと)のことも、当然ですが好きになれません。
鷗外は自分が受けたのと同様に、於菟にも学齢前から英才教育をほどこしますが、父親が津和野藩開闢以来の秀才だったのと違って、息子は普通の英才でした。それでも、祖母であるみねは、毎日いっしょに学校へ通って、於菟のする勉強を廊下で学びます。夏も冬も雨の日もなので、見かねた先生は、どうぞ中へお入りくださいとすすめますが、みねは頑として廊下で頑張ります。こうしたことが、さらにしげさんを怒らせます。
この鷗外の母も寄る年波には勝てず、やがて世を去ります。千駄木の家は、とうとうしげさんの天下です。最期までみねは家計を嫁に譲りませんでしたが、しげさんが取り仕切ったところで、やはり上手く行きました。
結局、しげさんは自分と夫の間に入ってくる、どんな人も許せなかったのです。鷗外の愛を完全に独占したかったのですが、そんなことは不可能でした。そもそも鷗外という人の器が、学問上でも人間的にも桁外れに大きかったので、夫を独占するということ自体が、まったく絵空事だったのです。それでも、そうしなければ気がすまなかったのですから、しげさんは、我儘で弱い人だったのです。それでも、それを正直と言って許されるのであれば、誰よりも正直な人であったと、於菟は言っています。
さて、しげさんが一家の主婦の座についたのも束の間で、4,5年して鷗外も亡くなります。ふたたび回ってきた春もみじかい春でした。腎結核でした。
これまでに於菟、長女の茉莉は結婚して家を出ています。次女・杏奴と次男・類がいっしょにいますが、しばらくすると千駄木の家は、鷗外が主だったころの面影はすっかりなくなります。杏奴は花嫁修業のため家にいます。類も、中学に行けなくなり、絵を習い始めます。そのうちに茉莉が離婚して帰ってきます。
この家は、朝になっても誰も出かけてゆく者がない家でした。 |
| |
|
| |
| |
森しげ伝 5 <茉莉を引取りましてございます>
鷗外は結核が腎臓におよんで亡くなりましたが、しげさんも腎臓のわるい人でした。夫が亡くなってからは、気の毒なくらいにがっくりと老いて、たびたび尿毒症を発症するようになります。もともと人付き合いのいいほうでもなかったので、孤独になります。同居していた先妻の子・於菟が、かわいい孫たちを連れて出て行き、さらに孤独になります。結婚しても育児・家事全般において、さっぱりだった茉莉が、子供をおいて家に戻ってきたのもショックでした。
茉莉の夫は帝大の文科を金時計で卒業するほどの人でしたが、茉莉がここまで家事ができない女だとは知りませんでした。しげさんと次男・類が茉莉のところへ遊びにゆき、食事して花札やトランプをしているうちに子供は寝てしまいます。茉莉の夫の山田珠樹(たまき)は、茉莉に早く寝かせてこい、と小声で言いますが、茉莉は動きません。子供が風邪を引くのではないかという気遣う本能が欠落しているのです。夫はもう一度言いたいのですが、そうすれば、しげさんが立ち上がるので言いかねています。それを次男の類は傍らで、はらはらしながら見ています。とうとう夫が「早く二階へ連れてゆけ」と大声を出しますが、それでも茉莉は「うーん」と言うだけで動かないのですから、座は白けてしげさんたちは帰ることになります。
こんな調子ですから、茉莉は縁を切られても文句をいえません。しげさんは「茉莉を引取りましてございます」と親戚や、知り合いに頭を下げてまわります。
茉莉がこうなっては次女・杏奴の嫁ぎ先が危ぶまれます。類をつけてフランスに絵画留学させることにしました。破れかぶれのばくちですから、親戚一同は冷眼無言で見守るだけです。ふたりはパリに二年間遊びましたが、「他人同士だったら、結婚していたよね」と言いあうほど気が合い、つよい絆のごときものが生まれました。
その間に茉莉は、もう一度、仙台に住まう男性に縁づいて嫁ぎますが、「ここには歌舞伎座も三越もない」
「なら、三越へいらっしゃいな」と体よく東京へ帰されます。
しげさんは、「また茉莉を引取りまして・・・」と挨拶する元気もありません。知った顔に会うのがいやで、芝居にも行かなくなります。
茉莉は千駄木の家に三たび帰って元気です。ここでは好きな時間に寝て起きて食べることができる。毎日、デパートと芝居に行って、面白楽しく暮らして、お金の心配もない。お金の心配がないのは、鷗外がこの事あるやもしれずと、生前に利殖してくれたおかげでした。時代も大正から昭和のはじめにかけて、インフレと好景気の時代で、利子だけで一家が暮らして行けて、元金は減らなかったと類は書いています。千駄木の家に通った幸田露伴も「鷗外は利殖のできる男だ」と、いくぶん軽蔑をこめた眼で見ていましたが、今やこうしたお金が、娘や息子を蝕んでいます。
|
| |
<写真・左から類、杏奴、茉莉、於菟> |
|
| |
| |
森しげ伝 最終章 <空を泳がせて羽織をはおると、きれいな風が起るようだった>
しげさんは、鷗外の建てた千駄木の屋敷にあって、だんだんと孤独になり、健康を損なってゆきます。腎臓の病でした。
茉莉は、母親・しげについては、色の黒いことを除けば本当に美しい人だったといっています。美人といっても、優にやさしい美人ではなく、火がついた時には何をしでかすか分らない美人で、かつ自分の気に入った相手に対しては、度を過ぎたお人好しになる、妲己のお百タイプです。出かけるに際して黒縮緬の羽織をはおるとき、空を泳がせて背中からふわっと羽織ると、きれいな風が起るようだったと、母の美しさを活写しています。
しげさんは、中味に凄いところのある美人でしたから、歯に衣をきせずに物を言いました。加えて愛嬌がちっともなく、ものの言い方も切り口上です。ものを断るときにも遠まわしに断ることがなかったので、鷗外が諾しているのに、奥さんが出しゃばって断ったと言われました。また冗談にまぎらわせて上手に皮肉を言う人がいると、これも火の出るように怒ったと、茉莉が書いています。
今でいうなら発達障碍という分類があって、しげさんは、これに類する人だったでしょう。ただし夫が鷗外という文壇の巨人で、なおかつ忠義と孝行の権化でしたから、少しあるしげさんの良いところも消し飛んで、見えなくなってしまいました。森鷗外の妻に対する世間の評価は、悪妻の典型で、徹底的に夫の親孝行の邪魔をしたというところでした。それに加えて美人でしたから、その悪妻ぶりは拍車がかかって伝えられたのです。
私が長々と森鷗外の妻について書いたのも、ここに理由があります。今でも、見るべきところが多々ありながら、自分の中にある如何ともしがたいもののために、生き難い人生を歩いている人はたくさんあって、そうした人達に、私はわたしの治療院で会っています。鷗外のように、寄り添って歩いてくれる者があれば、その歩みはずいぶんと楽になるのです。
そして、ここが肝腎のところですが、それは他人でなくてはだめなのです。肉親が寄り添っても駄目で、よそから来た他人が,その人の味方にならなければ意味がないのです。鷗外も結婚生活の経験から、妻に慈しむ心を向ければ、その心が些かでも楽になることを知って、そのようにした節があります。その一方で、歌を添削したり、胸に思うことを小説に書かせたりしています。
この心理機序は鷗外も同じで、鷗外の心理描写にすぐれた諸作品は、しげさんとの葛藤に満ちた生活のなかで生まれていると於菟は看破しています。この大作家も、書くことで救われていたわけです。
次女の杏奴が嫁いでから、しげさんの腎臓はいよいよ悪くなりました。茉莉も類も、病人の看護はできませんから、嫁いだあとも杏奴が看病にやってきました。杏奴はこれより先、洋画家の小堀四郎と結婚しています。やがて身ごもりますが、これ以上は無理というところまで大きなお腹をかかえて、杏奴は看病に来ます。尿毒症で意識が混濁するなかで、しげさんは杏奴を捜し求めますが、そんなある日、枕元の類に「茉莉をたのむ」といって、しげさんは息をひきとります。杏奴の出産のひと月後でした。しかし、しげさんは、この孫の顔を見ていません。昭和11年四月のこと、56歳でした。
最後に、於菟の言葉を引きますが、この人も鷗外がなくなった後にはしげさんと心置きなく話をすることがあったといいます。そうしたときには元来、心に汚れのない人だったので、安らいだ時の笑顔には、非常に美しく尊いものがあったと書いています。しみじみといい言葉です。
|
| |
|
| |
| |
森於菟「父親としての森鷗外」
森茉莉「記憶の絵」
森杏奴「晩年の父」
森類「森家の人々」
山本夏彦「最後のひと」 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |